視察前日の30日(日)の夜11時前に、盛岡のホテルに着きました。さすがに、東京とは違い、夜の冷え込みは結構厳しく、真冬の寒さは大変なものと感じました。
翌朝8時20分から、岩手復興局で、山下岩手復興局長から、幹部職員のご紹介を受け、その後に概況説明を受けました。説明の途中で、職員の方から、予定の時間ですからと出発を促されました。三陸の沿岸線に出てゆくには、盛岡から2時間はみておかなければなりません。
最初の視察地は、復興支援道路(釜石道路、釜石西IC)の事業中の工事現場でした。平成30年に、釜石道路は開通予定と伺いました。

復興支援道路の事業について説明を受ける
東日本大震災で、東北地方は津波による甚大な被害を受けました。このため、東西に、三陸沿岸道路、いわゆる復興道路359㎞、(岩手県内213㎞)この道路が縦軸、そして宮古盛岡横断道路66㎞、釜石秋田線(釜石花巻延長80㎞)が横軸となり、いわゆる復興支援道路と呼ばれています。
この工区は6㎞ですが、全体としては、花巻、遠野、釜石をつなぐ、先程お話しした釜石花巻道路です。この横断軸の強化によって、災害後方支援拠点と沿岸部を結ぶことになります。
北上市、金ヶ崎町などの内陸部の製紙工場、スチールコード加工場、自動車組立工場と釜石港をつなぐ物流の拠点となります。これは「命の道」とよく言われますが、救急医療施設への搬送時間が大幅に短縮されることになります。
私は道路は、「あらゆる力の源泉」と思っております。強い風が吹き荒れる中、工事関係者の皆様は、黙々と事業推進につとめておられました。
途中で釜石市の上中島災害公営住宅の視察を行いました。第1期は、平成25年5月より、入居を開始されました。3650㎡で54戸です。第2期は。14600㎡で156戸です。
私がなぜこの場所を視察したかったのかは、かつて災害特別委員会や決算委員会でも、このことに関連して質問をしたことがあるからです。
応急仮設住宅は、阪神淡路大震災の頃は、1戸あたり270~280万円かかりました。しかし今日は、1戸あたり撤去費用も含めると700~800万円かかると言われています。年老いた被災者の方々に、仮設住宅を提供するならば、むしろ20年程度暮らすことができる簡易住宅(恒久住宅)を建てた方が有効ではないのかと考えております。
無論、私有地の上に建てることは私有財産の形成、保全につながり、法律の問題、そして制度の問題にも関わって参ります。
そして、もうひとつ指摘させて頂きたいのは、住宅復興には、スピードが何よりも求められるということです。スチール工法を用いることで、約5ヶ月の工事期間で、復興公営住宅が竣工したということです。
これは、コミュニティを非常に大切にした住宅であり、広々とした空間の中に立っており、一部の棟と棟がデッキでつながれていました。そこから、環境の良さを私なりに感じ取りました。
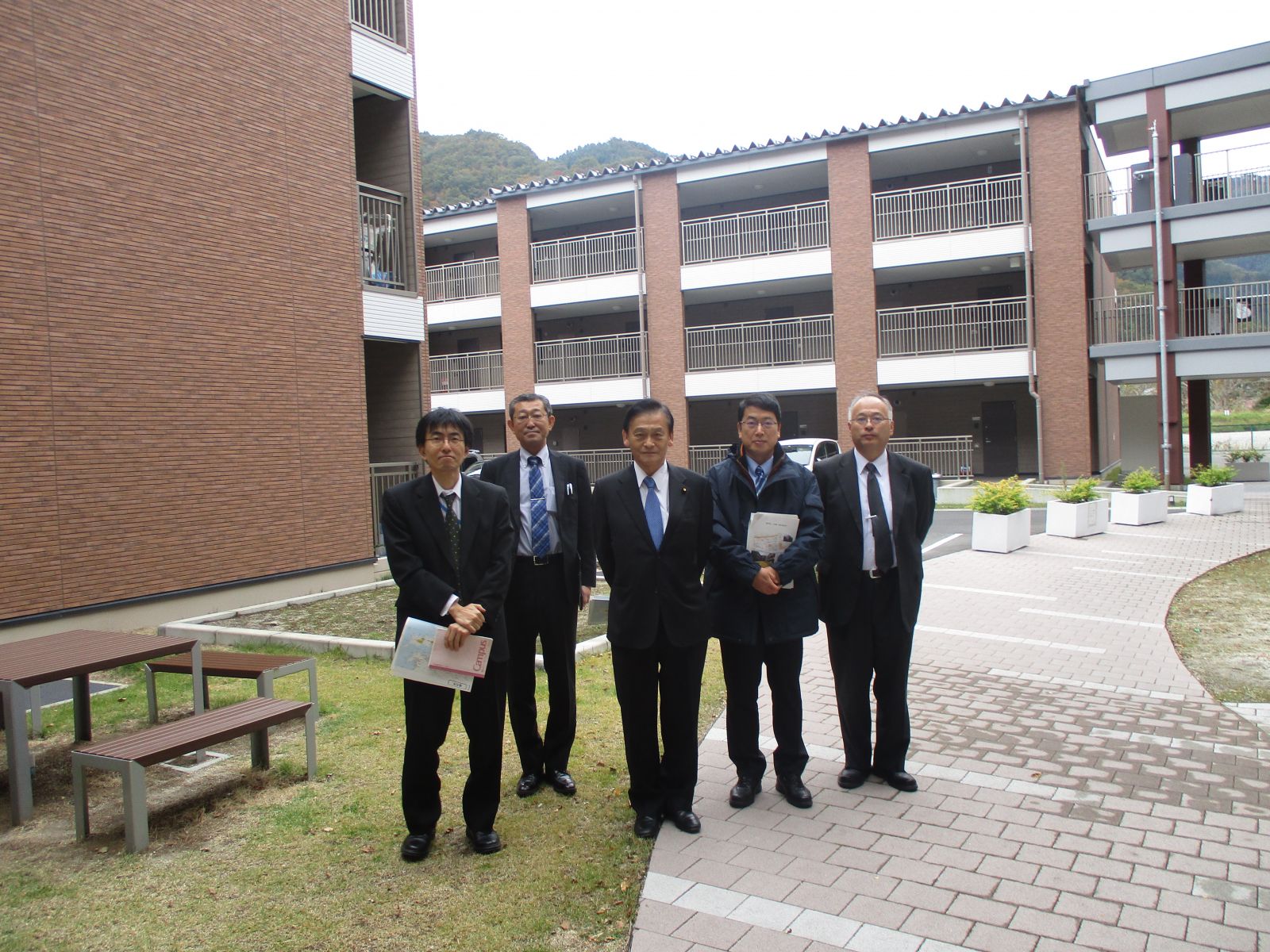
スチール工法の上中島復興公営住宅を視察
昼過ぎに盛駅に到着しました。JR東日本大口復興企画部長、柴田震災復興計画室長、尾関東北運輸局長のお出迎えを頂きました。ささやかな出張視察ですから、恐縮したところです。盛駅から大船渡駅まで、1駅間ですが、BRT(バス高速輸送システム)に乗車致しました。
かつてのJR大船渡線の鉄軌道を、バス軌道にあらため、出発をしました。沿岸自治体、JRとが議論の末、平成27年12月25日、BRTによる本格復旧で合意しました。
大船渡線が、盛駅まで開通したのは、実に1935年のことです。長い歴史があります。地元の皆様にとりましては、様々な思いがおありになったと思いますが、後世、BRTが「英断」として評されるよう、BRTが地元の皆様や観光振興に貢献してくれればと願うところです。
BRTから降車した大船渡駅前では、髙・大船渡市副市長、尾関・東北運輸局長からそれぞれの取組について説明をおうかがいしました。大船渡駅前地区の土地区画整理事業は、既に相当程度進捗しており、今後、商業施設等の移転、建設が行われる予定のようです。
他方で、BRTの走行路線を挟んで標高の高い山側が住宅区域、海側が商業区域になるため、これまで職住一体で営業を行っていた地元の事業者の方々にとってみると、住宅と店舗が分かれる形での生活を強いられることになるという課題があるともうかがいました。
BRTの駅を中心として一から始めるまちづくりは新たな試みであり、行政としても周到な計画と細心の注意、最大限の支援が必要になると感じました。

三陸鉄道・大船渡線盛駅のBRT乗り場にて
陸前高田市では、甚大な被害を受けた高田松原地区を訪問しました。震災追悼施設の慰霊碑に手を合わせた後、復興まちづくり情報館において、国土交通省から出向されているという長谷部・陸前高田市副市長から震災前後や緊急対応期の状況、復旧・復興の状況等に関する説明をおうかがいしました。
その後、震災前には陸前高田市のインフォメーションセンターの役割を果たしていた道の駅高田松原「タピック45」の遺構や、百数十年に一度の津波にも耐えられるという防潮堤の建設現場を見学させていただきました。
陸前高田市の復興のシンボルとも言える「奇跡の一本松」のあった高田松原地区では、復興祈念公園を整備する計画があります。同市は、震災において特に甚大な被害を受けた地域ですが、巨大な防潮堤や土地のかさ上げ工事が未だ広範囲に行われている様子を目の当たりにして、改めて被害の深刻さに思い至るとともに、復旧・復興事業の完成まで相当の時間を要するという印象を受けました。

「奇跡の一本松」を背に
一日も早い陸前高田市の復旧・復興が実現するよう、私も復興副大臣、国土交通副大臣として懸命に取り組んでまいりたいと思います。
今回の東日本大震災の復興への取組状況に関する視察では、盛岡市を出発した後、既に大部分が開通した復興支援道路と復興道路を利用して、沿岸部の3市を視察することができました。今後もできる限り頻繁に現地へ足を運び、現地のニーズ把握、国政への反映に努めてまいりたいと思います。
