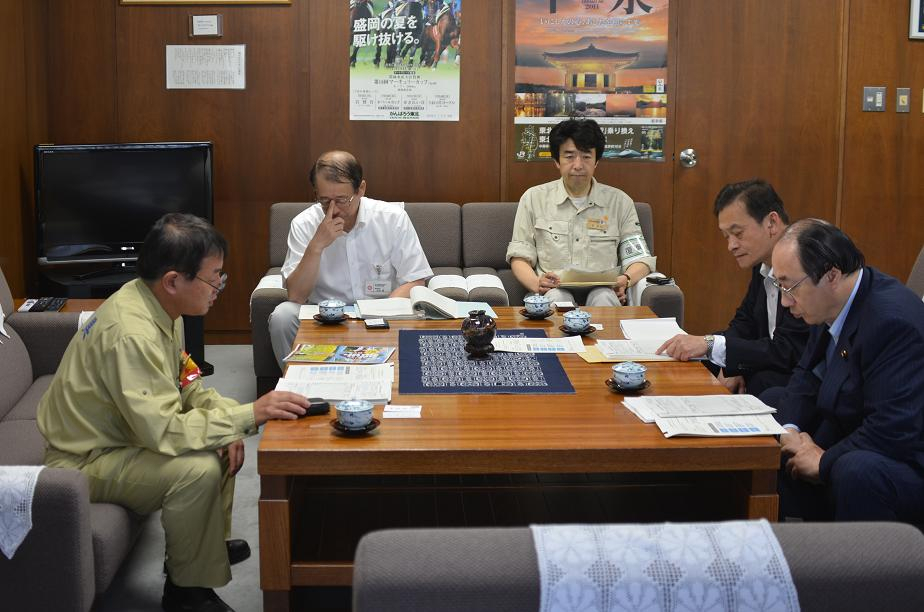
二日目は岩手県庁を訪問しました。
岩手県のGDPは約4兆円ですが、今回の東日本大震災で岩手県の一年分のGDPが消えてしまったそうです。岩手県海岸部のストック(固定資産)の約50%が失われました。ちなみに宮城県では約25%と言われています。
岩手県の上野善晴副知事は、「海岸の被害総額は宮城県の方が大きいですが、被害そのものの実態はむしろ岩手県の方が甚大とも言えます。我々は岩手復興計画として最初の3年、中間の3年、最終の2年と8年計画を組みました。10年は待っていられないという県民の要望にこたえたものです。」とのことでした。
さらに防災監は「100%災害のない街づくりはできないので、岩手県は『減災』という考え方で復旧・復興を成し遂げたい」と語られました。
漁業については、宮城県では約800億の水揚げがあり、岩手県の水揚げは約400億です。ただし、宮城はほぼ半分が沖合い漁業なのに対し、岩手県ではアワビ・ワカメ・ホタテなど養殖漁業・定置網漁業など沿岸漁業が中心であり、沿岸漁業だけで見れば宮城と同規模なのです。
おのずから宮城県と岩手県では大型船の占有率も異なっており、水産加工施設の復旧が進めば、立ち直りは宮城県より岩手県の方がかなり速いだろうという力強い言葉もありました。
上野副知事からは、あらゆる分野において復興実現をするためのノウハウをもった人間が少ない、つまり専門家が少ないということもお聞きしました。
このため今、国交省、UR、海岸の専門家、街づくりの専門家など、各町に2人ずつ派遣して復興計画を策定し、またその実行向けて日々必死の活動をしておられるとの話がありました。
宮古市で聞いた瓦礫処理の実態調査については、岩手県では7町村が県との委託契約なしで処理を市町村独自で進めているとのことでした。
また今回、衛星写真から倒壊家屋などの実態調査が進んだとの話をききました。多く運ばれてきて残ったままになっているヘドロについては、焼却して埋め立てをしたいということでした。
釜石での話同様、こうした塩分を含んだ瓦礫やヘドロは、焼却した場合やはり炉を損傷させてしまうので頭を痛めているとの話がでました。
今、除塩の研究を進めているそうですが、ヘドロは抜水処理が難しいということや、また瓦礫についてはアスベストなどの対策も講じないとならないという話もありました。
特に岩手県としては最終処分場をどこに求めるかということは、国が主体となって広域調整・広域処理をしてほしいとの要望が出されました。そして除塩についての技術開発を、国を挙げて進めてほしいとのことでした。
今、再生可能エネルギーが盛んに議論されていますが、岩手県の災害復興公営住宅には、太陽光パネル設置を義務付けたいとも述べられました。
そして宮古市で聞いた補助要項の件ですが、上野副知事からは、「瓦礫処理の補助要綱はすでに5月には出ており、補助対象も決まっております。概算払いも行っております。」とのことで、こういう点においては、一番大事な事業や施策についての連絡調整がなされていない一面があるようでした。
震災後の混乱というのは阪神淡路大震災でも、当然起きたことであります。今を生きている人々は多くの肉親・知人を失っておられます。悲しみ背負いながら、復興に向かって歩み続けられております。そのことを脳裏に焼き付け、私も阪神淡路大震災を遥かに超える被害を受けた東日本地域のために、復興に向けて努力を続けます。
*フォトギャラリーに写真をアップしました
活動報告
2011-07-21
岩手視察 3
